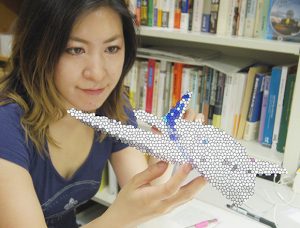
「異なる文化を尊重し互いに理解しあいましょう」では片付けられない「はざま」に生じる不可解さや滑稽さ、不甲斐なさ、そういうザラっとした感覚が人類学に進むきっかけでした。
なぜ専門に人類学を選んだのですか?
私は高校からカナダに留学し、クラスメイトの半分以上が移民や留学生という環境で3年間を過ごしました。学校は「多文化共生」「異文化理解」といったものに意識的で、Multicultural Weekや“Asian New Year”の催しなどが毎年ありましたが、それぞれの文化を尊重し合い理解を深めましょう、というノリに違和感を感じていました。「異文化理解」の名の下に何か重要な差異や類似が隠蔽されているのではないかという感覚が、イラン人の友達からラマダン明けにもらう激甘お菓子や、韓国人の友達のお母さんが作ったキンパを食べていると、どこからともなく気まぐれに顔を出してくるような感じです。そんな関心?悩み?について話した優秀な進路指導の先生から、大学ではcultural anthropologyを勉強してはと勧められ、そこから気付いたら博士課程まで来ていました。
現在どんなテーマで研究をしていますか?現在の研究テーマに行き着いたきっかけは?
学部生の頃は人やモノの越境的な移動に関心があったので、卒論では日本人バックパッカーと、当時「外こもり」と呼ばれ、「バックパッカーから旅という要素が抜け落ちた」とされる人たちを題材に、「移動」について論じることを試みました。じゃあ、そうした移動を可能にする科学技術に今度は注目してみようということで、修士論文では、道路や鉄道、飛行機といった交通インフラの発展が、人の移動経験だけでなく、価値や認識、社会全体にもたらしてきた変化、そしてその変化が翻って交通インフラのあり方自体に変化をもたらすような相互影響関係について論じました。
博士課程に入ってからは、実際に新たな交通が開発される現場をフィールドにしようと思い、大規模な鉄道計画があるラオスを選びました。現在は、道路や堤防、ショッピングモールなどの建設を通して、ラオスの首都ヴィエンチャンの都市化と、こうしたインフラが、人とモノ、街との既存の関係を再構成し、どのように新たな関係を作り出していくのかということに注目して研究しています。長期調査は2012年6月から2014年9月までで一旦終了して、現在は博士論文執筆に向けて、バラバラの事柄を一つのストーリーへと積み上げていくための武器を探しているところです。


なぜ一橋社会人類学を選んだのですか?/一橋社会人類学研究室の特徴は何ですか?/一橋社会人類学に来て良かったことは何ですか?
数ある大学院の人類学研究室のなかで、一橋は「頭でっかち」と評されることもありますが、確かに理論的な話、あるいはそもそも理論と事例の関係それ自体も問い直すような議論をする機会が多いかもしれません。私自身、ラオス研究者としては地域研究者やある種のジャーナリストには全く及ばないかもしれませんが、こうしたトレーニングを一橋で受けたことで、人類学者だからできる「経済」や「民主主義」、「保険衛生」や「自然環境」のハナシがあり、それらが既存の「経済」や「民主主義」といったものの枠組みを問い直す可能性を有しているのだと考えるようになりました。
また、一橋大学大学院では、マーキュリータワー内に院生の研究室が確保されています。同じ社会学研究科の、歴史学や哲学、社会学といった異なる研究分野の人たちとシェアする一つの部屋で各自の机と本棚が用意されており、いわゆる「学際的」な環境になっている点も、一橋に来てよかったと思うところです。
フィールドワークで苦労したこと、フィールドワークの醍醐味は何ですか?
単に下調べが甘かったということもありますが、私がラオスへ調査に出かけた当初、鉄道について調査しようと思って行ったのに、鉄道建設が全く進んでいなかったということがありました。ガランとした駅舎から延びる3.5kmしかない線路を目の前に、不在のものについてどうやって人類学的な調査をするのかと内心爆笑でした。しかし、鉄道自体はできていないにもかかわらず、鉄道が様々なエージェンシーを発動するという点が面白いのではという先輩からの助言を受け、新たな気づきを得ることができました。人類学のフィールドワークが他の分野のフィールドワークと異なる一番大きなポイントは先に問いを設定してその答えを探しに行くのではなく、しばしば問い自体が現場から立ち上がってくるということです。そこで「くらす」ことが調査であるため、「おもしろセンサー」を常に作動させていなくてはなりません。ただ、「フィールド・マジック」みたいなものもしばしばあって、帰国してよくよく考えると、しょーもない問いである場合も多々あるので注意が必要です。

研究キーワード
インフラストラクチャー、都市、開発、交通、ラオス
